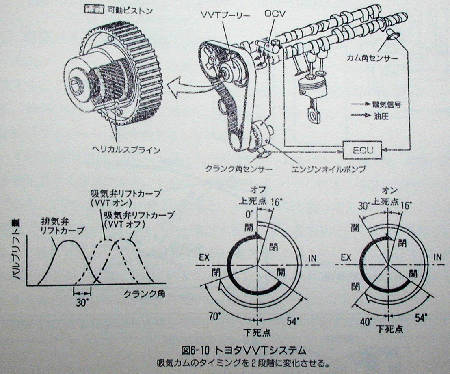可変バルブタイミングを考える
さて、またもや嘘かもしれない「やえ」の技術薀蓄です。今回はエンジン特性を大きく左右するバルブタイミングについて考えて行こうと思います。といっても、私は素人なので触りだけ(^^;。
エンジンの出力を上げる基本は、混合ガスをできるだけ詰め込んで、ギューっと圧縮してドカンと爆発させると思うのですが、混合ガスをできるだけ詰め込むにはどうしたら良いか、というところでバルブタイミングというのが大きく関わってきます。(ターボ装着とか排気量アップって話はここでは無視しましょう)。
ここでいうバルブタイミングというのは混合ガスの扉であるバルブの開き始め、閉じ終わりのタイミングと言う事にします。イメージ的にわかりやすいのは電車の自動ドアですかね。電車の空間が無限としたら扉が開いている時間が長ければ長いほどたくさんの人が入れます。
これがバルブの作用角ってやつですね。
もう1つ、本質的な意味のバルブタイミングというのがあります、これは作用角は同じで、開き始め閉じ終わりの真ん中である中心角を早めたり遅くしたりするものです。位相制御というやつですか。イメージ的には電車がホームに入ってきて停車してから扉が開くものと、ホームに電車が見えた時には扉がすでに開いている見たいな感じでしょうか(^^;。
世の中のエンジンは、高出力な物は基本的に作用角の大きいカムが入っていてバルブのリフトしている時間が長いです。もっと高出力を狙うにはさらに大きい作用角のカムを入れればいいかというと世の中難しい物で、最高回転数の引き上げ、吹き抜け吹き返しによるガス抜けに対して圧縮比のアップとかしないとパワーはそう上がらないと思いますが、この話はここでは無視して、ここでは作用角が大きいカムを組むと出力が大きくなると言う事にしましょう。
作用角の大きいカムを組むと、今度はエンジン回転が低い時に出力が下がってしまいます。これは混合気の流速が遅くなってしまうために、慣性でガスが入らなくなる、ガソリンの気化がしにくくなる等の理由からでしょうか。
つまり、高回転を狙ったら低回転はNGで、逆に低回転を狙えば、高回転がNGになってしまいます。
そのままでは回転全域についてパワーを得られ無いので可変バルブタイミングというのが出てきます。世の中にでてる物と言えばHONDAや三菱等でやってる可変作用角&リフト量タイプ、ローバーMGFの可変作用角タイプ、アルファロメオ、ポルシェ、日産(とりあえずこっち側にいれました)、マツダ、トヨタなんかでしている可変位相角タイプなんかですね。
HONDA VTECやその派生タイプはメカ的には複雑なんですが、低回転は作用角の小さいカム、高回転は作用角の大きいカムと使うということで、理解しやすいので割愛する事とします。MGFのVVCも同じく割愛して、ここでは可変位相角のタイプについてお話しようと思います。(単にやえがレビン乗ってるからだったりして(^^;)
やえ’レビンについているのはVVTという名の可変バルブタイミングシステムです。吸気側のカムプーリーを油圧で位相を30度速める構造になってます。
本の説明なんかだと上の図のようになってます。VVTがOFFの時は排気側バルブと吸気側のバルブが重なる量、オーバーラップが16度ですが、VVTがONになると46度に増えています。VTECと違って吸気カムの作用角は変わらないので250度一定です。
VVTのON、OFFで吸気側の位相が変わりオーバーラップ量が変化する事が確認しました。ではオーバーラップ量が増えるとどのようなメリットがあるのか考えてみましょう。
理科の実験でやったベルヌーイの定理というのがあります。これは流体の流れが速いほど圧力が下がるって定理です。飛行機が飛ぶのもこのおかげですね(^^)。
燃焼が終わり排気ガスを出すために排気バルブが開き、ピストン上昇とともに排気が始まります。この時、膨張した排気ガスがものすごい勢いで排気バルブから出て行きます。つまり、流速が速い→圧力が低い。排気バルブ付近の圧力が低いところで吸気バルブを開けば(オーバーラップが多い状態)吸気ガスが引っ張られるように燃焼室へ入って行きます。一部はそのまま排気ガスと共に捨てられてしまうんですが、吸気の流速がつけばタンブル流となって燃焼室に溜まるでしょう。
これがオーバーラップが無かった場合はピストンが下降し燃焼室内の圧力が下がってから吸気されることになります。より高出力を得るにはたくさんのガスを燃焼させないといけないのでピストン下降前からどんどんガスを入れたほうが有利ですね。オーバーラップさせるのは吸気ガスの初速をつけるためにやるって感じでしょうか。
それだったら、はじめっからオーバーラップを多くすれば良いじゃんと思う方もいると思いますが、そうするとアイドリング時や低回転アクセル開度小の時や高回転時に問題が発生します。
まず、アイドリングや低回転時ですがスロットル開度が少ない場合にオーバーラップさせると吸気側がひぱられてもガスは入って行きません(スロットルが開いてないから当然ですね)。それよか流速もつかないので、吸気ガスはそのまま排気ガスとして出ていってしまいます(^^;。となると、エンジンが不安定になるのは目に見えてますね。やえのレビンでアイドリング時等にオーバーラップさせてみると、当然アイドリング不調になりました。
次ぎに高回転時です。オーバーラップが多いのは一向に構わないのですが、ガスの充填効率を上げるには、下死点後にいかにガスを入れるかというのにかかってきます。オーバーラップが多いと吸気ガスの初速をつけ易くなると先ほど書きましたが、高回転時はそんな事をしなくてもすでに吸気の速度、慣性はついているので低中回転ほど重要ではないです。
それより、ピストンが下死点後上昇をし始めると、吸気バルブが開いていれば、回転が低い時は吸気側に押し返されるんですが(これを利用したのがミラーサイクルエンジンですね)、高回転時は吸気ガスに勢いがあるので燃焼室内に入って行きます(慣性加給)。理想としては、この勢いが無くなった所で丁度吸気バルブが閉じれば一番充填効率が上がるのでは無いでしょうか?。
ということで、やえ’sレビンで調べてみた結果、アクセル全開(VVT ON)で加速していき、約6,500rpm付近でVVTがOFFになるようECUが制御しているのを確認しました。5バルブ4A-GEだと、この辺りの回転がオーバーラップさせるより吸気カムを遅らせたほうが出力を得られるとメーカーが判断したんでしょうね。調べ方は、ECUのVVT出力信号とフレームアース間の抵抗を測るだけです。
では、5バルブ4A-GEのVVTがどのような制御になっているのかをまとめてみます。
回転数 | アクセル開度(小) | アクセル開度(大) |
アイドリング | VVT OFF | VVT ON |
低・中回転 | VVT OFF | VVT ON |
高回転 | VVT OFF | VVT OFF |
(水温等、温まってからでないとVVT ONにはならないようです。無理にONにしてみると、吹けなくなります(^^;)。
レビン・トレノ系のカムはAE86の頃は作用角が240度。これが5バルブ系になったら作用角が250度と大きくなっています。しかも、吸気バルブが1本増え、1.5倍まではいかないにしても(1つのバルブが小さくなるから)吸気の能力がかなり上がっています。つまり、より高回転型のエンジンに進化したわけで、その分低中回転が痩せてしまいます。その痩せた部分をこの可変バルブタイミング機構VVTというもので補おうというものです。
VTECみたく高回転出力を狙うものではなく、あくまでも低・中回転の出力を出すという目的の違いがあります(といっても歴史は遥かに位相型の方が古いのですが(^^;)。
VVTの機能をキャンセルして、作用角の大きいカムを組む人もいますが、サーキットユースならこうゆうのもOKだと思います。が、私みたく公道を走るのがメインの人はせっかくの機構を無効化するのは惜しい感じがします。自分のステージを見極めてチューニングしていかないと行けないですね。某マンガでVVTキャンセルなんて書いてたりしますが安易に真似をすると乗りづらい車になってしまいます。
 さて、話は変わりまして世の中にはVVTコントローラーなるものが販売されています。このVVTCというものは、ECUがけっこう細かい(でもないか?)VVT制御をしているものを、単純に設定回転より上ならVVT ON、それ以外はVVT OFFとするパーツです。 さて、話は変わりまして世の中にはVVTコントローラーなるものが販売されています。このVVTCというものは、ECUがけっこう細かい(でもないか?)VVT制御をしているものを、単純に設定回転より上ならVVT ON、それ以外はVVT OFFとするパーツです。
つまり、低回転でOFF、高回転でONにしてしまおうと言うわけです。今までの説明からすると高回転(6,500rpm以降)はVVTをOFFにした方がパワーが上がると書きましたが、そんな事をするとパワーが落ちるのでは?、ということで実験してみました。
シャシダイにかけるお金ももったいないので簡易に加速比較をしました。やり方はレビンに2名乗車し一人を後部座席ヘ。デジカメの動画撮影機能をもちいて2速べた踏みでタコメーターの針の上がりを撮影すると言うものです。ここで2速にしたのは1速だと吹け上がりが速いので誤差が大きくなるだろうと思いそうしました。測定ポイントは当然同じ所でしています。
これで、VVTCの設定回転3,000rpmにしたものと、VVT制御をノーマルの物で比較しました。やえのレビンには切り替えスイッチでVVTCを使うか使わないか選択できるようにしています。
その撮影したものをもとにコマ送りしてエクセルなんかでグラフを描いて比較しました。その結果、ノーマルのほうが遥かに高回転時の加速は良いです。つまりVVTCを付けるとMAXパワーはダウンします。
こんな事書くと「燃調はそれ様にとったのか?」とかと突っ込みが入ると思いますが、大半の人は同時にECUも交換なんてしないと思うので突っ込み無用です(^^;。
あ、やえのレビンでノーマルと変わっているところと言えば、エアクリーナーがきのこ型になっています(遮熱処理はしてますが・・・)。といことでこの状態での結果と思ってください。
で、話は変わって低回転です。こちらもノーマルならアクセルをガンと踏めばVVT ONになり強めの加速になるのですが、VVTCを装着しますと設定回転までVVTがONにならないため、そこまでの加速がかったるい感じです。また、設定回転になったら段付き加速をするのでやえ的には好みではないです。
では、この装置をつけると何が良くなるかですが、これは中回転域のアクセルとのツキの良さでしょう。
| VVTノーマル |
アクセル踏む
(VVT OFF) | → |
弱い加速
(VVT OFF) |
→
(VVT ONへ) |
強い加速
(VVT ON) |
| VVTC有り |
アクセル踏む
(VVT ON) | → |
強い加速
(VVT ON) |
|
|
てな感じで中間域ではVVTCを付けた方が遥かに良い感じになってくれます。体感的に速くなった感じがします。コーナーの多いミニサーキットなんかだと中回転域を多様すると思うのでVVTC有りの方がタイムが出るかもしれませんね。
ということで、位相型可変バルブタイミング機構のVVTについてかかせてもらいました。ではどのタイプの可変バルブタイミング機構が良いのか?を考えてみると、私の持論で「同様の事をするならシンプルな物ほど優秀だ」というのがあります(^^;。もしVVTがVTECと同等の出力とかを出しているのなら迷わずVVTと答えるのですが、どう贔屓目に見てもVTECには及んでいません。
可変バルタイ以外の要素が複雑に絡むので比較するのもおかしいのですが、カタログスペック上では4A−GEとB16Aは5psの差しかありません、しかし実際にこれらの車に乗っている人ならB16Aのパワーの凄さはわかると思います(つまり、普通の4A-GEはカタログスペックに遠く及びません)。
その位、低回転と高回転でカムを切り替えるというのが利に適った手法だと思います。
※かといって4A−Gがダメなエンジンじゃないですよ。パワーは劣ってもフィーリングの面ではすごく良いエンジンだと思っています。
トヨタはVVTの発展系として、VVTiというのを出しています。これはVVTが2段階の切り替えだったのに対し、VVTiは無段階に位相調整をかける機構に進化しています。しかも、中負荷時には60度も位相を早めて排気ガスを吸気側に戻し、再燃焼をかけるという事までしています。外部にEGRの装置を設置せずバルタイだけでしてしまうのに感心したのですが、あくまでもこの機構は環境、燃費面での配慮であり出力向上が目的でないように思われます。
とまぁ、VVT側が出力競争から降りたのかななんて思ったときもありましたが、最新の2ZZ-GEエンジンだと、VVTiとVTECを融合させたVVTLiという機構を作ってきました。個人的に「あ、あ、ついに真似をしてしまったか(^^;」なんて思ったりしましたが、その後HONDAも iVTECといって、VVTLiと同じような機構を出してきました。これからの高出力エンジンはこのタイプが主流になっていくんでしょうね。
ということで、可変バルブタイミングを考える編終了です。 |
 さて、話は変わりまして世の中にはVVTコントローラーなるものが販売されています。このVVTCというものは、ECUがけっこう細かい(でもないか?)VVT制御をしているものを、単純に設定回転より上ならVVT ON、それ以外はVVT OFFとするパーツです。
さて、話は変わりまして世の中にはVVTコントローラーなるものが販売されています。このVVTCというものは、ECUがけっこう細かい(でもないか?)VVT制御をしているものを、単純に設定回転より上ならVVT ON、それ以外はVVT OFFとするパーツです。